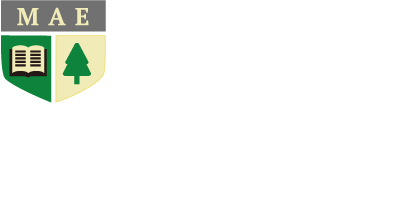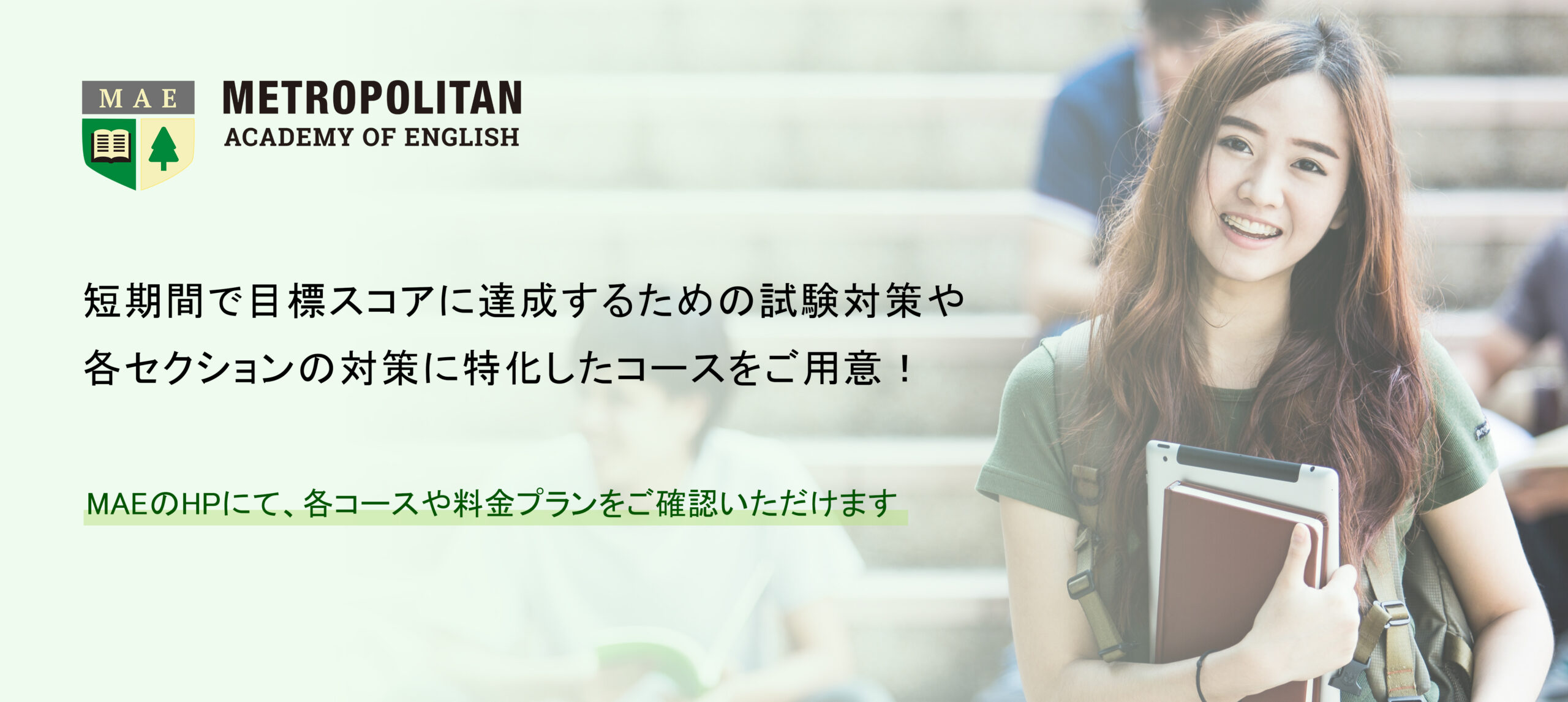抽象名詞が数えられる時と数えられない時
可算名詞と不可算名詞 ― 抽象名詞
英語では、名詞には数えられる名詞と数えられない名詞の二種類があり、それぞれ可算名詞・不可算名詞と言います。
可算名詞は、desk, chair, tableといった数えられる名詞のことを指し、その名詞が1つなら冠詞“a”、2つ以上なら複数形の”s”を付けることができます。
一方、不可算名詞は、coffee, tea, waterといった液体など数ではなく量で判断するものや、love, beauty, happiness, anger, hate, peace など、感情やアイデアを表す言葉を指します。
後者のような、原則的にひとつ、ふたつと数えられない抽象的な概念を表す名詞を抽象名詞と呼びます。
確かに、love(愛)やbeauty(美しさ)は、実在する物質のように数で表すことは難しいですね。
しかし、抽象名詞は使い方によって数えられる場合があります。
| 例1:She is a real beauty. / 彼女はとても美しい人です。 |
抽象名詞の “beauty” には「美しい人」という意味もあります。
概念である「美しさ」としてではなく、具体的な「人」を表す語として使われる場合は、可算名詞扱いとなります。
このように、抽象名詞には、可算名詞と不可算名詞の意味を両方持つものがたくさんあります。
上記以外にも、以下のような名詞が当てはまります。
| 可算名詞 | 不可算名詞 | |
| experience | 経験 | 体験 |
| application | アプリ(アプリケーション) | 応用 |
| promise | 約束 | 見込み、有望 |
| arrangement | 準備、手配 | 整理、配置、取り決め |
| proposal | プロポーズ | 申し込み、提案 |
| instruction | 命令、指示、説明書 | 教授、教育 |
| wish | 願望、希望 | (~したいという)願い |
| recommendation | 推薦状 | 推奨、勧告 |
| attitude | 態度、姿勢 | 気持ち、考え、意見 |
上記の名詞はどちらの意味でも使われることが多く、一つの個体として数えたい場合は可算名詞として、考え・概念として扱われる場合は不可算名詞となります。
その単語の意味が具体化・物体化すると、数えられるモノになるのです。
話者によって意図するものが違うので、時と場合、話者が話そうとする内容に応じて判断する必要があります。
また、抽象名詞の前に形容詞が付くと数えられることが多くなります。
これは、抽象名詞が形容詞によって限定されることで具体化するため、数えられるようになるという考え方に由来します。
| 例2:a deep sleep 「深い眠り」 |
「深い眠り」があれば「浅い眠り」もあることを暗示しています。したがって「眠り」に種類ができることで、sleepを可算名詞化させます。
| 例3:a thorough knowledge 「徹底した知識」 |
しかし、形容詞を伴うといって、全ての抽象名詞が数えられるようになるとは限りません。
例えば、”heavy traffic” 「交通渋滞」はheavyを伴っても”a” は付かず、どんな時も数えることができません。
その他、advice, information, news, luck, damage, equipment, fun, homework, work などは、形容詞が付いても数えられることは絶対にありませんので、覚えてしまいましょう。
まとめ・・・抽象名詞が数えられる時と数えられない時
抽象名詞が可算名詞として扱われる場合は以下の2パターン
具体的なものを指す場合
形容詞などを伴って具体化する場合
形容詞が付いても数えられない抽象名詞の例外を覚えるのが一番手っ取り早い!
慣習的な表現
“Rush hour”って不思議な表現ですよね?
通勤で車や電車が混雑する時間帯、ラッシュアワーって何時間にも及ぶし、hourは可算名詞。
“Rush hours” とは言えないのでしょうか?
答えは・・・言えません。
これは昔からの慣習的な言い回しです。
昔は午前9時から午後5時までしか仕事をしていなかったので、ラッシュアワーはおおよそ午前8時から9時までの約1時間と決まっていました。その頃の名残で、今でも “during (the) rush hour” や “at rush hour” のように常に単数で使用されます。
今のご時世、ラッシュアワーは何時間に渡るものですが、rush hours とは言わないのです。
昔からの名残で慣習的に使われ続けている英語表現は、意外と多くあります。
昔は “person” の複数形は “persons” でしたが、今では “people” を使います。
一方、現在でも、”persons” は非常にフォーマルな手紙などで使われてはいますが、私たちが日常的に耳にすることはあまりありません。
“persons” が使われるケースは、法律関係の書類で、特定の人数の人たち(例えば “7persons” など)や「人間の体」を表す場合がほとんどです。
慣習的に使われている表現をもう一つ挙げると、“in town” (in the town / in my town) があります。
「自分の住んでいる場所」という意味ですが、普通はtownの前に冠詞が入りません。
また、townだからといって、必ずしも(小さい)町を指すのではなく、より大きな規模の “city” を指すこともあります。場所の大きさに関わらず、「自分の住んでいる場所」を示す場合は “in town” と言うのです。
最後に “my cup of tea” という表現をご紹介します。
「私の好み」という意味のイギリス英語の表現で、イギリスでは頻繁に使われています。
イギリスでは、紅茶は昔から欠かせない飲み物であるため、そこから生じた言い回しです。
| 例4:He is not my cup of tea. / 彼は私の好みじゃないわ! |
言語の成り立ちには、歴史や文化と密接な繋がりがあります。
日本語は、英語のように名詞自体に冠詞のaや複数形sを付けることはしませんが、本は1冊、お箸は1膳、タンスは1棹(さお)・・・のように、ものの数え方については非常に多くのバリエーションがあります。
この違いは、そもそもその言語を話す人たちの生きてきた歴史や文化、考え方が違うことにより、言語に必要とするものが異なるために生じます。つまり、日本語圏と英語圏が違って当たり前ですし、スペイン語とポルトガル語が近いと言われるのも当たり前。こんなに場所も歴史もかけ離れているのですから、なかなか理解が難しいのも当然なのです。
じゃあどうすればいいのか?
ー覚えましょう。
少々乱暴ですが、例えば可算名詞や不可算名詞の捉え方でも、日本人の感覚からすると絶対に納得いかないところが出てきます。でもそれは上記の通り、そもそも言語の持つ背景が違うから仕方がありません。
「英語圏の人はこの単語をこういう風に認識しているんだな」と、日本語との比較をしたり、その違いに至る背景を想像することも、英語学習の楽しさの一つです。
ぜひ、色々と想像したり、自分の持っている知識と結びつけながらより多くの単語・表現・考え方を覚えてみてください。